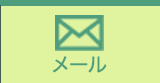戦後70年を迎える2015年。いま、戦争はどのように語られ、そして語り継がれてゆくのでしょうか。
このシリーズでは、一枚の写真とともに語り継がれる戦争の記憶を紹介してまいります。(なお、文章表現には当時の言い回しや、語り手ご本人の語彙を出来るだけ尊重しております。あらかじめご了承ください)
NO.03
「十五歳の志願兵 ~御蔵島の母へ~」
埼玉県 広瀬修さん(46)
御蔵島という島をご存知だろうか。現在、イルカウォッチングでにぎわうこの島は、伊豆諸島のひとつで周囲を断崖絶壁に囲まれた人口三四〇人あまりの島である。
父、広瀬匡利は昭和四年、この御蔵島に三人兄弟の次男として生を受けた。
この島には江戸の昔より続く「二十八軒衆」と呼ばれる古いしきたりがあった。平地の少ない土地柄、作物を収穫できる田畑の面積に限りがある。そのため人口 の増加を制限するために、島で暮らせる世帯数を二十八戸までとしたのだ。裏を返せば、家督を継ぐ長男以外はこの島に残ることを許されず、成人すれば島を出 て行かなくてはならない運命にあるわけだ。無論、次男である父も例外ではなく、尋常小学校高等科を出ると島を出て、ツテを頼って東京で丁稚奉公をはじめ た。
昭和十九年。十五歳になった父は、勤労動員で東京は大田区の下丸子にある大日本計機という軍需工場に勤務。そこで飛行機の速度計を作っていた。
ところが次第に東京への空襲が始まると、父は「今、私がここで空襲で死んでも、残された母にはなんの保証もない。しかし、同じ死ぬとしても兵隊として死ねば母へ恩給が支払われる」そう考えたという。
御蔵島で暮らす祖母のことを父はことのほか思いやっていた。というのも父がまだ幼い頃に祖父が早世したため、いわば女手一つで育て上げてくれたことへの恩が大きかったのだろう。
意を決した父は自ら志願し、十五歳の身空で横須賀武山海兵団(神奈川県)へ入団した。
勤務先の大日本計機を辞すとき、先輩や仲間たちから寄せ書きをいただいた。日の丸に「祝入團広瀬匡利君」「祈武運長久」と書かれ、父は送り出された。
海兵団では砲術を学び、その新兵教育の総仕上げは辻堂海岸(神奈川県)で行われた。海岸沿いの砂浜に土豪を掘り、松林をほふく前進し、三八式歩兵銃を抱え て駆けずり回った。過酷な訓練が終わると、銃を持って直線距離にしておよそ二十キロの道のりを走って横須賀まで帰ったという。
こうした日々の訓練を経て、昭和二十年に実戦部隊として神ノ池海軍航空隊(茨城県神栖市)、続いて鈴鹿海軍航空隊(三重県鈴鹿市)へと配属された。父は対 空機関砲の射手を務めたが、鈴鹿では、二トン近くある対空機関砲を据え付けるのに、土方もやったことから、それを見ていた町の人に予科練を文字って「どか れん」などとバカにされたそうだ。
そうした中、八月に十六歳で終戦を迎えた。しかし終戦後、父はすぐには故郷へ帰らなかった。三宅島で鍛冶職人としての修業を積もうと考えたのだ。野鍛冶といって、鎌や鍬などの農耕具をつくる職人である。
繰り返すが、故郷の御蔵島では長男以外は島を出ていかねばならない風習がある。次男である父は、戦後の混沌を生き抜いていくために手に職が必要だったの だ。ところが、父はここで結核を患ってしまう。重い症状だった。三宅島を出て東京の病院を転々とした父は、何度も死を覚悟したという。ところが最後にたど り着いた清瀬市の病院で、奇跡的に病状が回復した。この病院で知り合った看護師が、後に私の母となる。
こうして結核から立ち直った父は、ようやく御蔵島へ帰郷したのである。そして何を思ったのか、島の因習に反してここで暮らし始めたのだ。今でこそ観光地としてにぎわい、都会からの移住を受け入れているが、終戦当時それは非常に勇気のいる行為だった。
なにが父をそうさせたのだろうか。
おそらく、戦争、結核といった死と孤独に向き合った体験が、父の人生観を大きく変えたに違いない。母親への深い敬慕が、古いしきたりを超越したのではないか。
父と母は分家として肩身の狭い思いをしながら、私たち六人の子供を育ててくれた。そしてもうひとつ、本来ならば本家で暮らすはずの祖母が、習わしに反して 父とともに暮らす道を選んでくれた。これは極めて異例のことだと聞いている。生前、祖母は「生きている間は次男と暮らす。実家に帰るのは墓に入るとき」と 言っていた。その言葉通り、祖母は次男の家で天寿をまっとうした。
父はその後も島の教育長として勤めあげ、七二年の生涯に幕を下ろした。
しかし島の習わしによって、父の墓が御蔵島につくられることはなかった