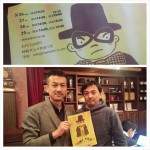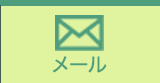ひとりネギ塩カルビ丼。(長文注意)
ここは秋葉原から徒歩10分ほど離れた、とある専門店。
サラリーマンが往来し、昼時には行列の出来る人気ぶりだ。
無愛想な店主が備長炭で一枚一枚丁寧に炙った牛カルビに、甘っからい秘伝のタレを絡めた絶品のカルビ丼を出す店。
かつて、このすぐ近くに11年間事務所を構えていた私にとって、実に馴染み深い店だ。
しかし、一年半ぶりに暖簾をくぐると、店内の様子は一変。赤い壁に漆黒の柱で統一された小洒落た内装。制服をきて、礼儀正しそうな店員が笑顔で客を迎えてくれた。
私は、店内をぐるりと見回し、カウンター席に腰を落とした。
たっぷりと煙とアブラを吸い込んでベタベタになったテーブルも、年季の入った椅子も見当たらない。
そして、あの煙の奥で黙々と肉を炙っていたオヤジの姿はなく、その場所には若き男が店主然と立っていた。
あのオッサン、まさか。
不安に駆られて店員に問えば、オヤジは引退して、それを機に内装も一年前に変えたと言う。
私は、いつも食べていたネギ塩カルビ丼を注文すると、すっかり様変わりしたカウンターテーブルに目を落とし、お茶をすすった。
無愛想なくせに、驚くほど気配りのできるオヤジだった。
以前、こんなことがあった。
カルビ丼を「並」にしようか「大盛り」にしようか、オーダーの時に一瞬迷ったことがある。結局、「並」を注文したのだが、出てきたご飯の量はいつもよりも幾分か多い気がしたのだ。
お勘定の時に、「今日の並盛り、ちょっと量が多かったですよ」とオヤジに声をかけてみた。
すると、オヤジは「お客さん、注文の時に大盛りか並盛りか一瞬迷われたでしょう? ですから、その中間の量にしたんですよ」と言って無愛想に笑った。
これには参った。
あの一瞬の迷いを見逃さなかったこと、そして気をきかせて並と大盛りの中間の量にして出したこと。
煙に巻かれ、黙々と肉を炙っていながら、そんなところまで見ていたのか。
私は、すっかりこの店の、いや、このオヤジのファンになった。
「お待たせしました」
取り止めもないことを考えているうちに、店員がネギ塩カルビ丼を運んできた。
出てきた肉の焼き色を見て、すぐにオヤジの炙ったそれとは違うものだと分かった。甘っからいタレの香ばしさが鼻腔をくすぐることもない。
味の記憶、匂いの記憶は、ウソをつかないのだ。
一瞬で「そうそう、コレでしょう!」と脳が反応するか、しないか。その瞬間を味わえれば、それだけで幸せだったのに。
ひとくち、口に運ぶ。
味はいいけど、私には別物。
店主が変わるというのは、店にとってリセットボタンなのだろう。
若き店主の下、小洒落た内装で、店員もスマートになった。
投資もして、カイゼンもして、経営努力を感じる。
しかし、どこかステレオタイプとなったこの店に、こみ上げる寂寥感を禁じ得ないのだ。
店を出るとき、「味が変わりましたね」と言おうとして、やめた。
この店は、これから新しいファンを獲得していくのだから、余計なお世話はやめよう。
願わくば、あの無愛想な親父の炙ったカルビを、もう一度だけ食べたかった。