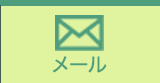ある方に自分史を見せてもらいました。仮にAさんとします。
40年近く前にAさんの大伯父が書き残したものです。
当時まだ高校生だったAさんに、大伯父はこの本に「Aくんへ」と一筆入れて手渡してくれたそうです。
本を拝見すると、巻頭には一家の古い写真、巻末にはしっかりと家系図もありました。
事細かく記録された文面からは、学者だったという筆者の几帳面な性格が窺えるものでした。
ところが、私がこの本を称賛すると、Aさんはふと表情を曇らせたのです。
実はAさんの父親は、この大伯父の家で育てられたのですが、その幼少期の不遇を今も忘れられないというのです。
大伯父は学者であり、実の子供3人を大学まで卒業させました。しかし、Aさん父親は同じ屋根の下で暮らしながらも、中学校までしか上げなかったのです。
Aさんのお父様がどれほど肩身の狭い思いをして幼少期を過ごしたのか、その後社会に出てどのようなご苦労をされたのかは、私には分かりません。
しかし、そのような境遇であったことは、父親だけでなく、息子であるAさんにとっても決して愉快ではない出来事だったはずです。
Aさんは「ここに書いてあることが全てではないのです」と言います。
つまり、Aさんの父親を中学までしか上げなかったことなど、この自分史には一切書かれていないのです。
筆者からすれば、弟が若死にしたのでその子供(Aさんの父親)を引き取り、戦後の荒波のなかで面倒を見たのだという自負があったのかもしれません。
自分史というのは、良くも悪くも筆者本人が自発的に語り継ぎたいことを選択し、書き残すものです。その反面、語られなかったことの陰にもまだたくさんの物語があるのも事実です。
この本はこれから先も筆者一族の歴史として残り、語り継がれていくはずです。しかも学者であったその几帳面な文面が説得力を増しています。逆に語られなかったことは形あるものとして残らないことになります。
私はAさんに次のようにお伝えしました。
「この本はこの本として、この先も大伯父様の歩んだ歴史として、また第三者から見れば資料価値もある立派な自分史として認められるに間違いありません。ま た、3人の実子から見れば、立派な父親像として後世へ語り継いでいくに値するものでしょう。そのことを受け止めた上で、Aさんのお父様も、ご自身の自分史 を綴られたらいかがでしょうか。どのような幼少期を過ごされたのか、社会に出てからどれほどご苦労があったのか、そうした中から奥様と出会い、Aさんを生 み育て上げてきた歴史があるはずです。その歴史を、今度はAさんが子供や孫へ、苦しい時に心の支えとなる一冊として、語り継いでいかれてはいかがでしょ う。きっと誇りに思って読んでくれると思います」
Aさんは少し微笑んで「この大伯父の自分史も、私は大切に語り継いでいきます」と仰ったのが印象的でした。