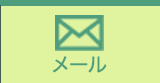戦後70年を迎える2015年。いま、戦争はどのように語られ、そして語り継がれてゆくのでしょうか。
このシリーズでは、一枚の写真とともに語り継がれる戦争の記憶を紹介してまいります。
NO.01
「内地勤務の過酷 ~祖父からの贈り物~」
東京都 関根孝さん(47)
祖父、関根健雄は明治四十年の深川区(現在の江東区)の生まれです。
実家は代々魚問屋を営み、たいそう裕福な家庭に育ったと聞いています。祖父は三人兄弟の次男で、柔道は五段、芸事にも秀でていました。
昭和十一年に深川の土地を売却すると、国立に引っ越しました。そこで広い土地を購入し、今で言う貸家業をやっていました。
第二次大戦が始まった昭和十六年、祖父は三十三歳です。柔道をやっていたので身体はがっちりしていたのですが、徴兵検査の時に持病を患っていたために乙種 合格でした。そのため直接的な戦闘行為は行わない内地勤務となりました。駐屯地の巡回、空襲被害の片付け、鉄道の復旧作業などが主な任務です。
終戦間際になると中央線沿線は爆撃を受けることが増えました。立川には飛行機工場があり、また川崎からは南武線で資材が運ばれてきます。つまり、この一帯は軍事工場の重要拠点だったのですから、狙われて当然だったのです。
あるとき、米軍機が故障したのか、パラシュートでアメリカ兵が空から降りてきたことがあったそうです。自分たちの町も子供も老人さえも容赦なく爆撃してき た敵兵ですから、民衆の手によって大変な目に遭わされていたことは想像に難くありません。そんなアメリカ兵を市民から引き離し、憲兵へ差し出すのも祖父の 仕事だったといいます。
しかし、中でももっとも過酷だったのが遺体を収容する仕事です。爆撃を受けた列車からいくつもの遺体を運び出したそうです。それはもう、言葉にはできない ような惨状だったはずです。当たり前ですが、遺体が自然に消えることはありません。誰かが必ず収容しているのですから。
そうして迎えた終戦。あたり一帯は焼け野原で、食べるものも仕事もなく、誰もが途方に暮れました。地主だった祖父は、土地を切り売りしながらどうにか生計 を維持していました。その後、国立の商工会議所を立ち上げたり、街づくりに奔走しながら平成十二年、九十三年の天寿をまっとうしたのです。
孫である私が生まれたのは、この国立です。つい十年ほど前までは家の裏に防空壕が残っていました。中央線沿線に面していた民家には、だいたい防空壕が掘っ てあったと聞いています。三十センチほどの厚みのコンクリートで覆われ、地下二メートルほどの深さはありました。子供の頃は遊び場でしたが、今は人手にわ たりマンションが建っています。
そんな私には宝物があります。中学生の頃に祖父からもらった一眼レフカメラです。当時としてはかなり高級なものでした。あの時の興奮は今でも忘れることができません。
あれから三十年が過ぎ、私はいまプロのカメラマンとして活動しています。
【昭和18年頃 内地勤務の様子】(写真左・関根健雄)