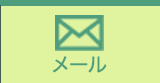戦後70年を迎える2015年。いま、戦争はどのように語られ、そして語り継がれてゆくのでしょうか。
このシリーズでは、一枚の写真とともに語り継がれる戦争の記憶を紹介してまいります。(なお、文章表現には当時の言い回しや、語り手ご本人の語彙を出来るだけ尊重しております。あらかじめご了承ください)
NO.05
偵察機「彩雲」に乗って ~鹿屋への思い~
東京都 大川和久さん(63)
昭和二十年、当時まだ十八歳だった父、大川二郎は鹿児島県の鹿屋海軍航空隊に所属していました。索敵(敵情視察)をする偵察機に乗っていたのです。
偵察機は「彩雲」といい、中島飛行場で三九八機製造されました。この「彩雲」はとにかくスピードが速く、そして飛行できる高度が8000~1万メートルと 高かったといいます。偵察機の任務は情報をつかみ、必ず帰ってくることでしたから、「彩雲」の性能の良さはまさにうってつけだったのです。
飛行機は三人乗りで、「操縦」「偵察」「通信」の役割分担がありました。父は偵察や通信を担当し、主に沖縄方面へ向かって敵艦の情報を探っていたといいま す。もちろん、油断すれば攻撃を受けて、「彩雲」といえども撃墜されてしまう危険があります。父は、万一通信が不良になったり不慮の事故があった時にそな えて、どこで何があったのかメモに残すよう命じられていたそうです。果たして緊急事態のさなかにそのような行為ができるのかとも思いますが、常に命懸けで あったことは確かだったと思います。
この鹿屋飛行場からは多くの特攻隊が出撃し、若い命が失われました。幸い父は特攻することなく終戦を迎えましたが、中には天皇の玉音放送を聞いたあとに死 地を求めてなのか、出撃していった人たちもいました。特に有名なのは大分から出撃した宇垣海軍中将による「彗星」十一機でしょう。彼らの心境を現在の私た ちがとやかく言うことはできませんが、痛ましい出来事でした。玉音放送をもって停戦命令となったかどうかは定かではありませんが、彼らの死は戦死としては 扱われなかったといいます。
この宇垣中将の特攻機を後から「彩雲」が追ったという手記が残されていて、そのエピソードは『最後の特攻隊の真実』(太佐順著・学研)に詳述されており、父大川二郎の記述も非常に多く見られます。この本の中で、晩年の父は次のように語っています。
「敵機艦隊の待ち伏せ場所を、いくら打電して知らせてやっても、どのみち、特攻隊員は皆死にゆく身でした。それを思えば、偵察機とはいえ、結局は死への道案内でしかなかったのではないか……と、今ではそんな思いもします」
父の出身は群馬県です。昭和二年に生まれ、栃木県の旧制中学を出て横須賀第二海兵団へ入団。海軍通信学校では階段を二段ずつ上るように言われたそうです。 懲罰では教官から「海軍バット」で尻をしたたかに叩かれるため、あまりの痛さにトイレでは座ることも立ち上がることもままならなかったそうです。天井から ひもが吊るされ、それにつかまって用を足したと聞きました。
そうした訓練を経て鈴鹿の海軍飛行機練習生となりました。その後、徳島海軍航空隊を経て鹿屋へ配属。第一七一海軍航空隊偵察第四飛行隊一等飛行兵曹として任務にあたりました。
戦争が終わると、父は鹿屋から飛行機を自ら操縦して厚木まで行き、そこから汽車で故郷まで帰ったそうです。国のために命をかけてきた者にとって、敗戦し生 き残ったことは顔を覆いたくなるほど恥ずかしいことだっといいます。しばらく故郷で過ごした後、父はふたたび鹿屋へと舞い戻り、そこで結婚して私が生まれ ました。
私から見た父の印象は、几帳面で実直。自分にも他人にも厳しい人でした。市役所に勤め、市長秘書を経て県会議員になりました。
そんな父の息抜きは、植木や生け花でした。裏山から枝ぶりのいい松やイヌマキの木を切ってきては、庭木に育てていました。
忍耐強く、涙など一度も見せたことのなかった父でしたが、私が心臓病で倒れ生死をさまよったと聞いたときは、涙を流して心配していたと後から聞きました。
父は平成十七年十一月十六日、七十八歳で他界しました。父の影響なのか、最近になって私もバラの会に入るなど、植物を愛でる心境が生まれました。
大勢の戦友を失ったこの鹿屋の地に暮らし、鹿屋の発展のために働くことが父のせめてもの弔いだったのかもしれません。